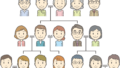テレビやニュースで「AI」という言葉をよく耳にしませんか?
「人工知能って何だか難しそう」「自分には関係ない話だろう」
そう思われる方も多いかもしれません。
しかし実は、お手持ちのスマートフォンを使って、今すぐにでもAIの便利さを体験することができるのです。
今回はAIをまだ利用したことのない人に向けて、スマホでAIに質問する方法とその便利な利用方法について分かりやすくご説明いたします。
AIで出来る事って何がある?
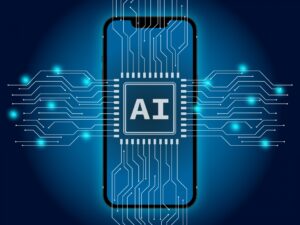
AIとは「人工知能」のことで、簡単に言えば「人間のように考えて答えてくれるコンピューター」です。
まるで物知りな友人に質問するように、AIに話しかけると、様々な質問に答えてくれます。
例えば「今日の天気は?」「風邪の時の食べ物は?」「孫へのプレゼントは何がいい?」といった日常的な疑問から、「この病気について教えて」「老後の手続きについて知りたい」といった真剣な相談でも可能な限り答えてくれるのです。
昔は図書館に行って調べたり知り合いに電話で聞いたりしていたことが、今では手のひらのスマートフォン一つで24時間いつでも解決できるようになりました。
スマホでよく使われるAI 3選!

スマホでよく使われるAIを3つ紹介します。
- Googleアシスタント
- Siri
- Aiアプリ
それぞれの使い方や特長を見ていきましょう。
1. Googleアシスタントを使う方法
多くのスマートフォンには最初から「Googleアプリ」が入っています。
その中に自動的に「Googleアシスタント」というAIが入っています。
使い方はとても簡単です。
Android端末の場合
- ホームボタンを長押し、または「OK Google」と話しかける。
- マイクのマークが表示されたら質問を話す。
- 知りたいことを少しゆっくりではっきりした話し方で話す。
- 回答文が表示される。
iPhone の場合
- Google アプリをダウンロードする。
- アプリを開いてマイクのマークのボタンを押す。
- 知りたいことを少しゆっくりではっきりした話し方で話す。
- 回答文が表示される。
実際に「今日の天気を教えて」「近くのスーパーはどこ?」と話しかけてみてください。
音声で文字で回答してくれるので、文字を読むのが大変な時にも便利です。
2. Siriを使う方法(iPhone の場合)
iPhoneをお使いの方は、Siriという優秀なAIアシスタントがすでに入っています。
Siriの使い方・始め方
- 設定からSiriを有効にする必要がある場合があります
- サイドボタンを長押し
- 「Hey Siri」と話しかける
Siriは日本語での質問にとても上手に答えてくれます。
「明日の予定を教えて」「タイマーを5分セットして」「息子に電話して」など、日常生活の様々な場面で活用できます。
3. 生成AIアプリを使う方法
より高性能な生成AIアプリも登場しています。
生成AIアプリは検索したりするだけでなく、自分で考えて文章やマニュアルなどを作ってくれるAIです。
これらのアプリは無料でダウンロードでき、より詳しい質問にも答えてくれます。
おすすめの生成AIアプリ
- ChatGPT:世界中で話題のAI。複雑な質問にも丁寧に答えてくれる
- GoogleGemini:ChatGPTと同等のAI
- Claude:文章作成や相談事に特に優れたAI
- Bard:Googleが開発した最新のAI
これらのアプリは音声に対して文字に変更することはできますが、そのあとは送信ボタンを押す必要があります。
また回答も文字で送られてきます。
AIへの上手な質問の仕方

AIに質問する時のコツをお教えします。
難しく考える必要はありませんが、少し工夫するだけでより良い答えが得られます。
具体的に質問する
質問はより具体的に話す方が良いでしょう。
- 「血圧が高い人におすすめの食べ物を3つ教えて」
- 「東京から大阪まで新幹線で行く料金と時間を教えて」
- 「60歳の男性におすすめの趣味を教えて」
- 「近くの歯医者をさがして」
簡単な質問ではあなたの意図が分からないので、的外れな回答になる事もあります。
- 「健康について教えて」→一度目であなたの知りたい情報が出ることは少ないでしょう。
- 「旅行について教えて」→「旅行とは何か」などを回答される可能性があります。
- 「趣味について教えて」→AI自身の趣味として架空の話をする場合があります。
- 「病院を探して」→何科なのか分からないので、総合病院などが表示される。
背景情報を伝える
質問時にAIにあなたの状況を教えると、より適切な答えが得られます。
特に生成AIのような高度な回答文を求める場合は効果的です。
AIは人間ではないので質問者の心情や状況まで理解できません。
ですから自分の今の状況なども含めて質問すると、より求めているものに近い回答が得られます。
- 「60歳の主婦です。膝が痛いので、家でできる軽い運動を教えて」
- 「定年退職した男性です。時間があるので新しい趣味を始めたいです」
上記のように「60才」「女性」「膝が痛い」「家で出来る運動」の4つのキーワードから検索して、回答文を出してくれます。
分からない言葉があったら遠慮なく聞く
AIの回答文に専門用語や分からない言葉があったら、その部分を聞いてみましょう。
Aiは相手の知識レベルも瞬時には判断できません。
ですから専門用語を使う場合があります。
例えば「ラジオボタン」などと言われても、何?あのラジオ?となりますよね。
そんな場合は「ラジオボタンって何?」と聞き返してください。
すると「一つだけ選べる丸い選択ボタンです」と回答してくれます。
一度回答を出してくれたあとでも「私は素人です。もっとわかりやすい言葉で書いてください」と書けば書き直してくれます。
相手はAIなのでしつこくても怒ったりしませんから、何度でも気にせずに質問することができます。
検索手段としてのAI活用事例
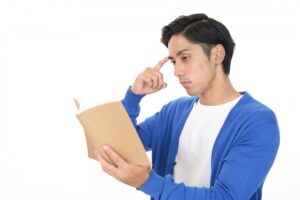
AIを検索手段として使用する場合の活用例を紹介します。
- 健康管理に関する質問
- 料理のレシピ検索
- 孫や家族とのコミュニケーション
- 趣味の相談
- 手続きや制度の確認
特に生成AIは高度な内容での回答が得られます。
健康管理に関する質問
「この薬の副作用について教えて」
「腰痛に効く体操を教えて」
「血圧を下げる食べ物は?」など、健康に関する疑問を気軽に相談できます。
自分で検索しても見つけ出しにくい場合に便利です。
ただし、重大な症状がある場合は、必ず病院で医師に相談することが大切です。
料理のレシピ検索
「冷蔵庫にキャベツと豚肉があります。簡単な料理を教えて」
「一人分の煮物の作り方を教えて」など、手持ちの食材で何が作れるか聞いてみましょう。
分量や手順も詳しく教えてくれます。
孫や家族とのコミュニケーション
「中学生の孫が喜ぶプレゼントは?」
「息子の誕生日メッセージを考えて」
「家族旅行におすすめの場所は?」など、家の行事の企画のヒントも得られます。
趣味の相談
「ガーデニング初心者におすすめの花は?」
「将棋のルールを教えて」
「読みやすい小説を推薦して」など、新しい趣味を始める時の相談相手としても活用できます。
手続きや制度の確認
「年金の手続きについて教えて」
「確定申告の必要書類は?」
「介護保険の使い方は?」など、複雑な手続きについても基本的な情報を教えてもらえます。
AIを使う時の注意点

AIはとても便利ですが、使用する際は以下の点にご注意ください。
- 個人情報は話さない。
- 医療や法律の専門的判断は実在する医師・弁護士に相談する。
- 情報の確認をする。
個人情報は話さない
住所、電話番号、銀行口座番号、パスワードなどの個人情報は、AIに教えないようにしましょう。
あなたの質問や回答が外部に出ることはありませんが注意が必要です。
またAIへの質問に慣れてしまった頃に外部サイトへの入力時に、重要な情報を書いてしまう癖を作らないようにする必要があります。
一般的な質問や相談にとどめることが安全です。
医療や法律の専門的判断は医師・弁護士に相談する
AIは一般的な情報は教えてくれますが、専門的な診断や法的判断はできません。重要な決定をする時は、必ず専門家に相談しましょう。
情報の確認をする
AIが教えてくれた情報が常に正しいとは限りません。重要な情報については、他の情報源でも確認することをお勧めします。
まずは気軽に試してみましょう

AIと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実際に使ってみると「こんなに簡単だったのか」と驚かれることでしょう。まずは簡単な質問から始めてみてください。
最初におすすめの質問例:
- 「今日の天気はどうですか?」
- 「風邪の時に良い食べ物を教えて」
- 「近くのコンビニはどこですか?」
- 「今日は何の日ですか?」
これらの質問に慣れてきたら、だんだんと複雑な相談もしてみましょう。AIは24時間いつでも、あなたの質問を待っています。
新しい技術と上手に付き合う

AIは私たちの生活をより便利で豊かにしてくれる技術です。年齢を重ねたからといって、新しい技術を避ける必要はありません。むしろ、これまでの人生経験を活かしながら、AIという新しい道具を使いこなすことで、さらに充実した毎日を送ることができるでしょう。
スマートフォンでのAI利用は、思っているよりもずっと簡単です。まずは今日、お手持ちのスマートフォンに「こんにちは」と話しかけることから始めてみませんか?きっと新しい発見と便利さを実感していただけることと思います。
この記事のポイント:
- AIは難しいものではなく、日常生活の便利な道具
- スマートフォンがあれば今すぐ始められる
- 質問の仕方を工夫すると、より良い答えが得られる
- 個人情報の管理と情報の確認は忘れずに
- まずは簡単な質問から気軽に試してみる
年齢に関係なく、誰でもAIの恩恵を受けることができます。新しい技術を味方につけて、より豊かな生活を楽しみましょう。